こころはHeartにありや--1
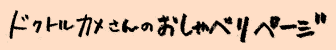 |
■心臓移植
麻酔科医の恵子は自分の心臓が拡張型心筋症に侵されているのを十分に知っていた。父親もこの病気で57才の若さで死んでいた。医大卒業後2年目までは何とか仕事にも研究にも耐えることができたが、それ以後は体調がすぐれない日々を過ごすことが多くなり、自分に残された時間が多くないという不安を絶えず感じていた。心筋症は心筋の変性により十分に血液を全身に送り出すことができなくなる進行性の病気であった。このため、やがては歩くことさえままならなくなり。ベッドにしばりつけられ死を待つ生活を覚悟せねばならない。
そんなある日、恵子は医大の麻酔科 杉木教授の紹介でアメリカの病院で心臓手術を受けることを勧められ渡米したのであった。幸運なことに恵子とHLAの型が合うドナーが渡米3月後に現れ、無事、心臓移植の手術を受けることができた。そして半年後には日本に帰国することができた。もちろん、手放しの喜びではない。一生、免疫抑制剤を飲みつづけなければならなかったし、そうしていてもいつ拒絶反応が出てくるか分からない不安はあった。しかし、近年、日本の製薬会社が開発したFK506などの優れた免疫抑制剤が市販されるようになってきたため、拒絶反応の発現を10%程度にまで抑えることができるようになってきていた。しかし、反面、免疫を抑制する影響で癌になる確立も確実に高くなるのである。
無事、アメリカから帰国した恵子は再び、麻酔科医として病院で働くことができるようになった。ところが、一緒に手術室で働いているナースたちが恵子の立ち振る舞いが以前と何となく違っているように感じだしたのであった。それはなんといったらいいだろう、一言で表現すれば恵子が男っぽくなったような印象を皆が受けるようになったことである。
がに股でスタスタ歩く、態度がなんとなく横柄である、手持ちぶさたなときはバスケットのシュートのまねをする、ナースたちをみる目つきが以前と違っていやらしくなっているのである。それでもみんな、主治医も含めておそらくそれは免疫抑制剤を飲み続けているせいだと好意的に信じていた。
しかし、恵子自身も何となく以前、すなわち心臓移植を受ける前との違いに不安を抱くようになっていた。前は耳鼻科や眼科の女医たちと違ってビールなんかは宴会があるとき以外を除いて自分から進んで飲むようなことはなかったし、ピザやとりの空揚げをコーラとともに食べるようなこともなかった。音楽もクラッシックよりロックやジャズを聞くと自然に体がリズムをとるような感じになっていた。
もしやと思い、恵子は5月の連休を利用して再びアメリカへ飛んだ。目的はドナーが果たして誰だったか探し当てることであった。
■ドナーと自分
恵子は手術を受けたマサチューセッツ総合病院の心臓移植を担当するコーディネーターに面会し、ドナーが誰であったのか教えてくれるよう必死で頼んだのだった。もちろん、ドナーが誰であったかは教えてはいけないことになっていたが、コーディネーターは日本からわざわざ飛んできた恵子の迫力に根負けして、ドナーは交通事故で死んだ18才の白人男性でイニシャルがWFであったことを漏らしてくれた。それだけ分かれば探し出すのは難しくないと彼女は考えた。さっそく、恵子はボストン市立図書館に足を運び、地元の有力新聞ボストングローブ市の手術当日の記事に目を走らせた。やはり、あった。当日、ビルという白人青年がボストン近郊の町セーラムでスポーツカーを走らせていて事故を起こし、近くの病院に運ばれていた。恵子はレンタカーを借り、高速道路を北に向かって車を走らせた。
セーラムは古くは魔女狩りで有名な町で今でも魔女の館や魔女の地下牢博物館などがあり、アメリカ東部を訪れた観光客をひきつけていた。セーラムに着いた恵子は早速市役所に向かい、イニシャルWFの青年の家を聞いてみた。気のいい市役所のおばさんは分厚い眼鏡をかけて住民台帳を見ながら青年の家を見つけ、自分で案内してその家まで連れていってくれた。
家には青年の母親が一人で住んでおり、恵子を歓迎してくれた。そして、死んだ息子の自慢話をはじめた。
身長は190cmで高校のバスケットボール部に所属していたビルはまたピザとコークが大好物でガールフレンドを乗せていつもスポーツカーを乗り回していたということであった。
恵子は背中から冷たい汗が幾筋も流れ落ちるのを禁じえなかった。
